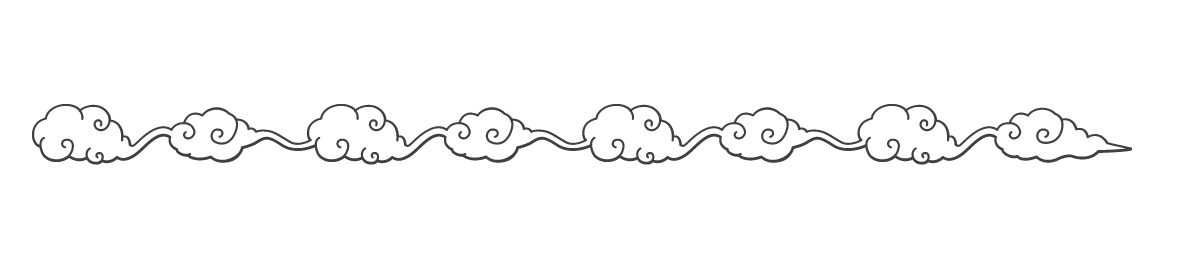馮夢龍『情史』の訳書を探していて、飯塚朗訳『情史 中国千夜一夜物語』(新流社、1947年)を購入しました。
探している時に、どの挿話が収められているのかが判らなかったので、ここに目次を掲載しておきます。
范希周(山賊の妻なれど)
申屠氏(ある漁師の妹)
張小三(娼妓のまごころ)
王善聰(男装の麗人)
趙判院(名妓瞥見)
蘇城丐者(蘇城の乞食)
江情(江上の戀)
劉堯擧(舟子の娘)
紅拂妓(紅拂を執る女)
許俊(柳は風に)
凌延年(遊蕩兒)
杜枚(詩人餘聞)
謝希孟(有情學者)
王 元 鼎 (女ごころは)
長沙義妓(長沙 の 義妓)
啞娼(啞藝妓)
老妓(老妓)
圖形詩(繪畫と詩篇)
寄內詩(妻に寄するの詩)
寒梅(寒梅)
孟姜(長城の恨)
司馬才仲(夢で來る女)
王生(えにしの夢)
西湖女子(西湖の女)
楊玉香(葉末の玉)
心堅金石(心の化石)
雙鶴(めをと鶴)
趙汝丹(戀の道草)
于祐(紅に題す)
非烟(貞操問答)
金山僧惠明(女の復讐)
鉛山歸(嵐の夜話)
蘇子鄕(蘇武餘話)
趙淸献(將軍有情)
散樂女(鳥迫ひ女)
張紅紅(女樂士)
滿少卿 (呪殺された滿郞)
舘陶公主(妃殿下色ざんげ)
魏靈太后(魏の太后)
王鉄(裏からのぞいた役人)
章子厚(男地獄)
林澄(戀塚)
雲英(逢初橋由來)
劍仙(女仙劍の舞)
花麗春(髑骼の化粧)
翠薇 (琴に慕ひ寄った女)
桂妖(桂の精)
菊異(菊の 精)
龍陽君(龍陽石)
朱凌谿(朱凌谿)
譚 意 歌 (うき川竹)
雁(雁の話)
燕(燕の話)
虎 一(虎の話其の一)
虎 二(虎の話其の二)
情盡橋(柳橋)
狂燭(狂燭)
醉輿妓圍(醉輿と妓圍)