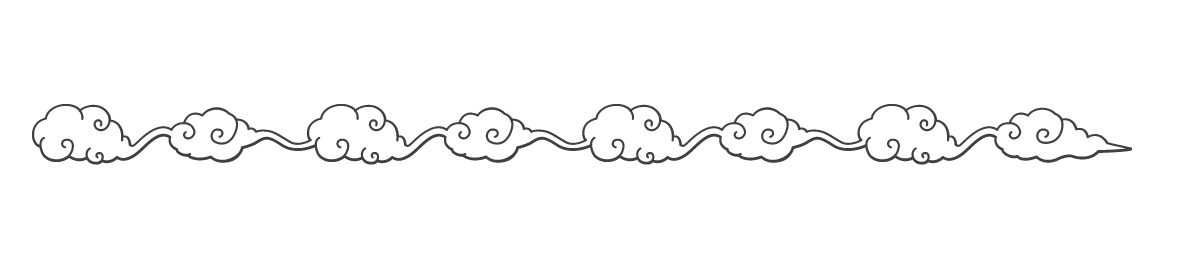前回に続いて、雑誌『新小説』第27巻8号に掲載された「聊齋妖話」から「畫皮」です。
「聊齋妖話」には、前回の「胡四姐」と、この話が収められています。今回の方がちょっとエグいかも。また、現在の基準からすると不適切な表現も見られますが、あらかじめご了承ください。
聊齋妖話 伊藤貴麿
畫皮
太原の王生と云ふ者が、未明に表に出た所が、一人の娘に遇つた。包みを抱へてたつた一人で急ぎ乍ら、甚步きにくさうにして居る。生は急ぎ走つて追い着いて見ると、十六ばかりの嬌娜姿である。心が切りに動いたので聲をかけて見た。
「姐さんはどうしてこんな夜明に、獨りで行きなさるんだい。」
すると女は云つた。
「他人には妾の悲しみは解りませんわ。問はないで頂戴。」
「姐さんに何んな悲しい事があるのか知らんが、事によつちあ、お力にならうじあありませんかね。」
女はしほしほとして云つた。
「妾の父母はそりや慾張りで、妾を金持ちに賣つたのですの。すると其所の本妻が妬いて、朝晩打つたり罵つたり、それはひどいので溜り兼ね、遠方へ遁げようと思ひまして。」
「そして何所へ行きなさるんだい。」
「ただ遁げ出して來たんですもの、何所つて的などありませんわ。」
「そんなら、私の宅が近いから、来なすつたら。」
女は喜んで從つた。生は女に代つて包みを持つてやつて、案内して一緖に歸つて來た。女は室に人氣のないのを見て、
「お家族の方は。」と訊ねた。
「此所は書齋だからさ。」
「本當に此所はいい所ですのね。妾を可憐さうだと思つて救つて下さるんなら、誰にも云はないで頂戴ね。」
生は承知して、それから一緖に寢起きした。女を密室へ匿して置いてから二三日經つたが誰も氣づかない風であつた。
生は此の事を鳥渡妻にほのめかした。すると妻は、きつと大家の勝妾《おもひもの》かも知れないから、と云つて、追ひやる事をすすめたが、生はきかなかつた。
或日市へ行くと道士に遇つた。と道士は、
「何かに御遇ひなすつたかい。」
と、愕いて問ふた。
「いいえ、何にも。」
「貴方の身體に邪氣が立昇つて居ますぞお隱しなさるな。」
「いいえ、何にも。」
と生は再び力を込めて云つた。すると道士は向うへ行き乍ら、云つた。
「ああ惑へる哉! 死將に臨まんとするも、悟らざる者有り!」
生は其の言葉を變に思つて娘を疑つて見たが、又思ひ直して、あんな美しい娘が、どうして妓怪《おばけ》でたまるものか。道士は威かしを云つて飯の種にでもする氣だらう。……と考へて、やがて歸つて來て、書齋の門迄來ると、門は閉つて居て這入る事が出來ない。これはと鳥渡變に思つて、垣を踰えて室の門へ來て見ると、亦閉つて居る。そと行つて窓から窺つて見る、あつと驚天した。中には面が眞蒼で、齒が鋸のやうにギサギザした一匹の鬼が、榻上に人間の皮を擴げて、釆筆を執つてそれを畫どつて居た。そして筆を擲げ打つて、皮を手に取つて着物でも振るやうにして、身體に掛けると、忽然として一個の美女となつた。此の狀を見て、大いに懼れて、這ひ出すやうにして、急いで道士を追つたが、往つた先が解らない。漸く尋ねあぐんだ上、ふと野原で遇つたので、這ひつくぼつて救ひを乞ふた。すると道士は、彼奴を娘の身體から追ひ出しても、又苦しまぎれに、代りの者を求めるやうな事があつては、又其の者を殺生する事になるからと云つて、生に蠅拂ひをくれて、それを寢空の外に懸けるように云つて、又後程、靑帝廟の所で會はうと約束した。
生は家へ歸つて來たが、書齋に這入る事を爲得ないで、內室の方に寢て、拂子を懸けて置いた。暫くして戶の外でがたがたと云ふ足音がした。生は自分は恐はかつたので、妻にそつと窺ばせて見た。すると其所へ女がやつて來て、拂子を見て、よう進まないで、齒をむき出して良久しく立つて居たが、引返して行つた。そして暫くすると又やつて來て、罵り出した。
「へん、道士などが嚇かしたつて駄目なこつた。どうして餌食を逃すものか。」
かう云つて、拂子をばりばりと碎き、寢門を破つて、生の牀の上に飛び上つて、生の肚を引裂いて、心臟を摑み上げて往つて了つた。妻は喫驚して、わつ! と泣いたので婢が燭を持つて這入つて來た。見ると、生は巳に息絶えて其所らぢう血だらけなので、氣もぼんやり、泣かうとしても聲も出なかつた。翌日生の弟に使をやつて、走つて道士に吿げさせた。道士はこれを聞いて赫つと怒つた。
「汝、悪鬼め! 慈悲を垂れてやれば、つけ上りやがつて!」
そして生の弟と一所に飛んで來たが、女はもう其所には居なかつた。道士は首を仰いで四方を眺め廻して云つた。
「幸に未だ,遠くは遁げては居ない。南隣りは誰の家かね。」
弟は、それは私の宅ですと云つた。と道士は、今はお前さんの所に居ると云つたので、弟は喫驚してそんな筈はないと云つた。と道士は訊ねた。
「先き方から誰か知らない者が來やしなかつたかね。」
「私は靑帝廟へ往つて居ましたので詳しい事は存じません」
そこで、弟は問ひ訊しに歸つて往つたが、少らくして、引返して來て、
「居ました居ました。今朝一人の婆さんが來て、女中奉公をしたいと云つたものですから、家內が止めて置いたのです。現に今居ります。」
と云つたので、道士は「そ奴だ!」と云つて、一緒に往つて、道士は木劎をとつて庭の眞中に立てて叫んで云つた
「悪鬼め!俺の拂子を返せ!」
すると部屋に居た姿さんが惶てて眞蒼になつて、門を出て逃げやうとした。道士は追つ驅けて、遂に之を擊つて地に斃すと、ずばりと人間の皮から脫けて、化つて厲鬼となり、のた打つて呻めいて居る樣は、豚のやうであつた。道土は木劍を以て其の首をせめると、瞬ち變じて濃い煙となり、地を這つて立昇つた。道士は一つの葫蘆《ふくべ》を出して、栓を拔いて烟の中に置くと、飄々然として、烟が吸込まれて行くやうで、やがて烟はなくなつた。道士は口を塞いでそれを嚢に入れた。又其の人間の皮を視ると、眉目から手足に至る迄、皆備つて居た。道士はそれを、まるで畫軸でも卷くやうに、さらさらと卷いて、やはり囊に入れて、別れ去らうとした。生の妻は門の所で拜んで迎へ、哭いて回生の法を嘆願した。道士は自分には出來ないと斷つた。餘り妻が悲しんで、地に伏して起きないものであるから、道士は暫く考込んで居たが、自分の術は淺くて、とても死者を生かす事は出来ない。が、私が或人を敎へて進せませう。其の人なら或は出来るかも知れない。往つてよく賴んで見なさい。と云つたので、其の人はどう云ふ人かと訊くと、市に糞土の中に寢たりして居る瘋者《きちがひ》が居るが、それに一つ哀れを乞ふて御覽なさい、然しよく云つて置くが、夫人《あなた》を辱めるやう事をしても、怒つてはいけませんよと云つた。生の弟も恰度其の男を知つて居たので、道士に別れて、嫂と一緒に往つて見た。すると往來に放歌して行く乞食が居て、鼻汁を垂れ、其穢なさ側へも寄れない程であつた。生の妻は膝まづいて進んで往つた。と乞食はからから笑つて、
「別嬪さん、俺いらが可愛いいのかね。」
と云つた。生の妻はここへ來た譯を吿げた所が、猶更からからと笑つて、
「お前さん、亭主はいくらでもあらあね。死んだ者を活かすなんて……」
生の妻は重ねて固く哀許した。
「ハハハ可笑しな人だね。死んだ者を活かせなんて、俺いらは閻魔様じやあるめいし。」
かう云つて彼の男は杖を以て生の妻を打つた。生の妻は痛みを忍んで、之を受けたが、段々見物の人が集つて來た。乞食はべつと痰を吐いて、それを差出して、喰つて見ろと云つた。生の妻は流石にたぢろいたが、道士の言を思ひ出して、强いて痰を呑込んだ所が、喉の中を、固い綿の團りのやうなものが、ごくりごくり下つていつて、胸の所に留つたやうな氣がした。すると乞食は大いに笑つて
「別嬪さんは俺いらが可愛いいと見えるて。」と云つて往つて了てた。後を尾けて往くと廟の中へ這入つたが、追つかけて見ると何所へ往つたのか姿が見えない。それからどんなに捜しても手掛りがない。生の妻は恥ぢ怒つて歸つて來て、夫を亡つた慘ましさを嘆き、痰を食つた恥を悔ひて、ぱつたり俯向けになつて、此の上は自分も死んで了ひたいと、搔きくどいた。それから死骸の血を拭つて死骸を處理しようとしたが,家人達はただ突つ立つて居て、近附いて行く者もない。妻は死骸を抱いて哭き哭き傷をうまく收めて、又止め度なく哭いて居た。と急に嘔き氣を催して、胸の中に塊りがあるやうに覺え、そして其れが突然、げろつと出て來て、首を廻す假もなく、生の裂けた腔の中に落ちた。喫驚して見てみると、それは人の心臟であつた。そして腔の中でぴくぴくして、未だ熱氣が躍つて居て、もやもやと烟のやうな湯氣が立つて居たので、これは不思議な事もあるものだと、急いで兩手で以て腔を搔き合せ、力一ぱい抱き締めたが、少し疲れてひるんで來た。すると烟が合せ目からすうすう漏れるので、絹の布切《きれ》を裂いて急いで束へて、手で以つて屍を撫でて居ると、段々溫くなつて來たので蒲團を掛けて置いた。そして夜中になつて視ると、鼻に呼吸《いき》が通つて居るやうで、夜明けになつて、遂に活返つたが、まるで言《もの》を云ふに、恍惚として夢のやうであつた。そして心臓のあたりに痛みを覺えると云つた。前に裂けて居た所を見ると、錢程の傷になつて居たが。直ぐに愈つて了つた。(了)