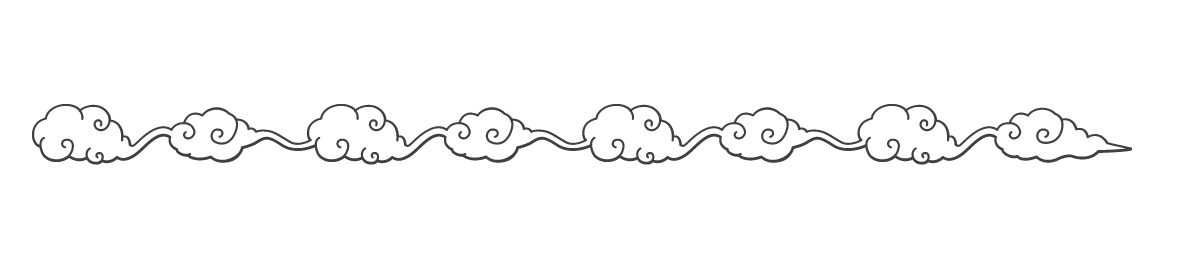今回は、前回の「王桂菴」と同じく、雑誌『新小説』28巻8号(大正12年8月)に掲載された「緑蔭雑筆」に収められた話の中から「三生」を載せます。三度の前世を憶えている男の話です。
綠蔭雜筆 伊藤貴麿
三生
湖南の某は能く前生三世を憶えて居た。第一世は役人となり或る時試驗官として、場に臨み、受驗生の文を採點した事があつた。其の時興と云ふ書生があつて、試驗を受けて落第し、憤懑の極死んで陰司に行き、訴狀を作つて閻王に訴へた。時恰も同病死者數萬陰府に滿みて、興の訴狀の一度投ぜられるや、聚散成羣して興を首とし、鬼嘯陰 殷々として閻羅府を動かさんばかりであつた よつて湖南の某は地獄に引かれて、閻王の前で對質訊問せられる事になつた。
「お前は何故これ等の書生を落第させたか。」
閻王は某に訊いた。
「私は試驗官となつた以上、どうして秀才を落し、凡庸を登第させる事がありませうか。然し、私の上には試驗官長が居ますから、その者が最後の擢黜を決めるのです。私はたゞ命のまゝに役目を果して居るに過ぎません。」
と某は答へた。
そこで閻王は又試驗官の長を召して、某の云つた事を吿げて訊た。
「私は試驗官を總べて、最後の斷案を與へるに過ぎません。もし佳章があつても、下役が之を薦めなければどうして私の目に入るでせうか。」
と試驗の主司は答へた。
「貴様達はそんなに罪を委ね合つて居ては果しがない。では二人共同罪にするぞ。」
と閻王は叱つて、笞刑に行はうとした。
これを見て居た興は、未だ憤懣を癒やすに足らず、大聲呶號したので、諸鬼も又それに和し 喧々囂々たる有樣であつた。閻王がそれを問ふと、興は抗議して云つた。
「罪が未だ輕きに失します。どうぞ兩眼を抉つて、文章を見る事が出來ないやうにして下さい。」
閻王はこれには同意しなかつた。と又諸々の亡靈は騒ぎ出した。閻王は云つた。
「彼等は佳文を得る事を欲しなかつたのではない。たゞ己の見識が足りなかつたのだ。」
「では心臟を抉つてやつて下さい。」
閻王は爲方なく、ニ人の袍服をはいで、白刃を以て胸を抉らしたので、二人は血にまみれて悲嗚を上げた。と亡者共はこれを打見乍ら、大いに快しとし、口々に叫んで云つた。
「吾々は怨みを抱いて泉下に來たが、今迄誰一人として、此の怨を晴らす者はなかつた。今興先生を得て、此の怨恨を晴す事の出來たのは、吾々一同の大いに喜びとする所である。」
そして、亡者共はどつとをめいて散つて了つた。某は刑が終つてから、今度は陝西地方の土民の子に生れて來た。彼が二十歲の時、地方に土賊が盛んに興つて、彼も又其の中に卷き込まれた。其のうちに官兵がやつて來て、大半の賊は俘擄にされた。彼も又俘掳にされた一人であつたが、自分は無理强ひに土冠の群に落されたのだから、言譯も立つだらうと思つて居た。さて官兵の將の前に引き出された時、ふと堂上を見ると、其の男もやはり二十歲ばかりである。よくよく見ると、それは以前の興であつた。某は喫驚して、あゝ駄目だ!と心に叫んだ。
果して他の俘擄は皆赦し放たれたが、某ばかりはどうしても辯解が容れられず、未だ因果が盡きないものか、とうとう斬罪に行れて了つた。
某は陰府に落ちて、今度は己が訴狀を作つて、興を訴へたが閻王は未だ興の祿が盡きないと云つて、きかれなかつた。後三十年待つて、興が陰府に來た時、某は大いに面質して、興の罪を嗚らした。そこで興は人命を草木の如く粗末にした罪によつて、次の世は畜類に落された。又、某も曾て父母を撻つた罪によつて同罪に落される事になつた。そこで某は、恐らくは興が再び自分に仇するであらうと思つて、自分を大きな獸に生れさせて吳れるやうに願つた。閻王はこれをきき屆けて、某を大きな犬にし、興を小い犬とした
某は北順天府の市中の犬となつて生れ、或る日街頭に伏して居ると、一人の旅人が南からやつて來て、腕に金毛の犬を抱いて居た。其の大きさは、やつと狸程であつた。某はちらりとこれを見て、あゝ興だな——と直ぐ見て取り、其の形が小いのに心易しとし、直ぐ樣飛びかゝつて嚙み附いた。と、小犬は素早く大犬の喉の下に喰ひ附いて、鈴のやうにぶら下つた。某の大犬はこれを振り飛ばさうと藻搔き、又市人も分けようとしたが及ばなかつた。遂に兩犬は其所に斃れて了つた。
かく命を終つた二畜は、共に冥府に行つて 互に閻王の前で爭つた。
「貴樣達のやうに、仇を仇で報じて居ては果しがない。」と閻王は云つた。「今度は兩人の間を和げる爲に、一方を他の方の娘の壻にして取らせよう。」
そこで某は慶雲といふ所に生れて、二十八の時鄕試に擧げられ、一女をもうけた。娘は生ひ立つに從つて、殊麗玉を磨くが如く、附近の世族は其の娟姿に憬れて、爭つて緣を結ばうとしたが、皆きかれなかつた。
其の後、某が隣り町に行つた事があつたが、其の時恰度採用試驗が終つて、第一番になつた、李と云ふ姓の者に會つた。よく見ると、それが前の興である事が直ぐ解つたので、自分の宿に招いて厚くもてなして、色々と訊ねた。そして未だ彼が獨り身であつたので、早速自分の娘との婚姻を申込んだ。世間の人は皆、これを見て、二人の前の因緣を知らなかつたので、彼が李の才に惚れ込んだが爲だとばかり思つた。
李は其の娘を娶つて、二人は仲よく暮したが、彼は才を誇つて娘の父を侮り、絕えて其の門を訪れる事をしなかつた。然し某はよくこれに耐えて居た。其の後壻の李は、出世も思はしくなく、落魄して居たが、某は李の爲に謀つて百計を盡し、終に李をして志を得せしめるやうにした。それから二人は實の父子のやうに仲よくなつたといふ事である。