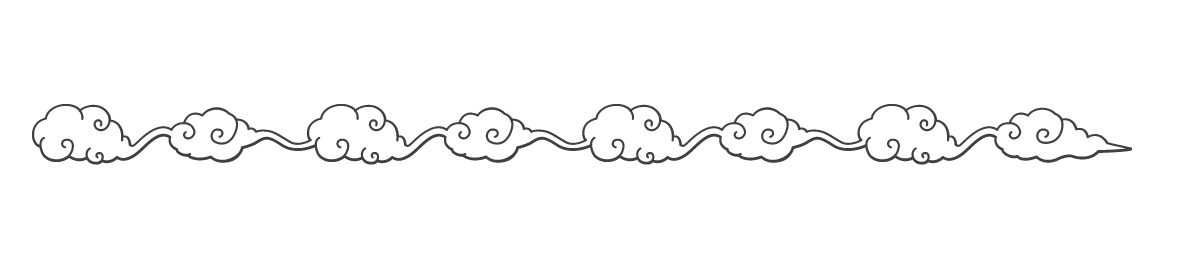今回も、雑誌『新小説』28巻8号(大正12年8月)に掲載された「緑蔭雑筆」から、「董公子」という話です。主人の首は斬っても関帝廟のそばに埋めてはいけませんという話...なのかな?『聊斎志異』巻六に収められています。
綠蔭雜筆 伊藤貴麿
董公子
靑州の董尙書の家庭は非常に嚴肅で、內外の男女はひと言も交す事を許されなかつた。或る日一人の婢と僕とが、中門の外で巫山戯て居たのを公子に見つけられて、ひどく、叱られて、二人共逃出して了つた。
公子は其の夜、近侍の童と一緖に書齋の中に寢たが、恰度酷暑の候であつたので、室の扉は皆開け放してあつた。と深更に及んで、童は牀の上に何か音のするのを聞いた。其の聲があんまり高かつたので、喫驚して眼を醒すと晝間の僕が何か一つの物を提げて、門を出て行くのが見えた。然し家人の事だから、深くは怪しまず、復眠り附いたが、突然靴音がどしどしして、赤面長髯の壽亭侯の像に似た一個の偉丈夫が人の頭とおぼしき物を提げて這入つて來たので、喫驚して床の中にもぐつて了つた。然し、物のひしめくやうな音が聞えて、恰も、着物を振つたり、腹をさすつたりするやうだつたが、暫くして靴の音も他の響も止んで了つた 童は首を伸して恐る恐る見廻して見ると、もう窓の上に曉の色が差して居た。ふと手を伸して床の上をさぐつて見ると、着衣がべとべとして居て、嗅いで見ると血腥かつたので、大聲で公子を呼び起した。公子が眼を醒したので、此の事を吿げ、灯を點して見ると、血が枕や蒲團に一ぱいだつたので、仰天したが、どう云ふ譯か解らなかつた。其の時けたゝましく、門を敲く役人があつたので、公子が出て見ると、彼人達はあつと魂消て、怪訝な風であつた。公子が詰ると、初めて吿げて曰つた。
「今朝役所の前で眞蒼な顏をして、自分は主人を殺して來たと大聲で叫ぶ者があるんです。皆が見るとその衣類に血が附いて居て、捕へて訊べると、貴方の家の者だと解つたのです。そして彼が貴方を殺して、首を關帝廟の側に埋めて來たと白狀したんです。行つて調べて見ると、成る程穴の土は未だ新しいが、首はなくなつて居るのです。」
公子はそれを聞いて、驚き怪しみ、走つて役所に行つて見ると、其の男は前に婢と巫山戯た男だつた。よつて昨夜からの不思議を話した所が、役人逹は惶き惑ひ、兎に角、其の男に重罰を喰はして放つてやつた。
公子は小人の怨みを結ぶ事を好まなかつたので、以前の婢を以て其の男に娶合せて、追ひやつた。すると數日經つてから、其の僕の隣りの者が、夜中に其の男が寐室の中で、あつとー聲呻いて、何か引裂かれたやうな音を聞き附けたので、急いで走つて行つて、呼んで見たが應じないので、扉を破つて這入つて見ると、夫婦諸共寢床迄、ずたずたに引裂かれて、其の切り口は、一刀のもとにぶつつりやられたやうであつた。古來から關公の靈現は數多くあるが、こんな不思議は未だなかつたといふ事であつた。