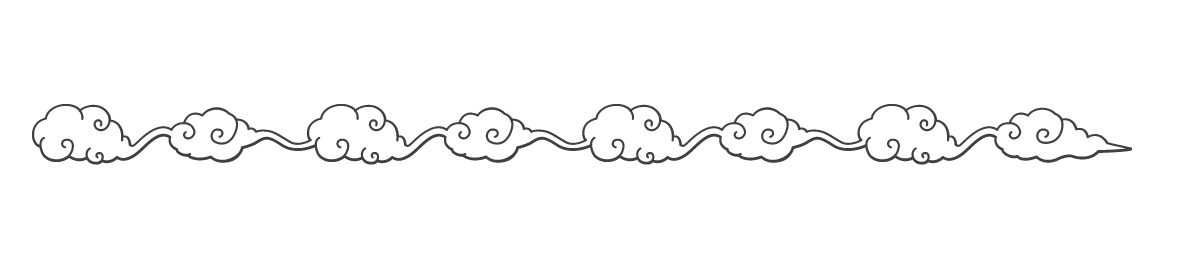今回は、『聊斎志異』巻十一「竹青」の翻訳です。行き倒れてカラスになり「竹青」という名の雌カラスとつがいになった男の話ですが、その後も紆余曲折があります。
管見の及ぶ範囲では、金の星社の『六年生の世界童話』世界童話名作選(1954年)が初出のようで、ここに掲載した文章も、これに拠っています。その後、一度文章に手を入れたものが「竹青」のタイトルで『少年少女のための世界文学宝玉集』上(宝文館、1956年)に掲載され、再び「竹青ものがたり」のタイトルで『中国童話集』世界児童文学全集12(あかね書房、1959年)、『世界童話六年生』(金の星社、1961年)に掲載されています。
竹青ものがたり
湖南省に、魚容という若者がありました。ある年、都へのぼって、官吏になる試験をうけましたが、不運にも落第し、そのうえかえってくる途中で、路用のかねもなくなつてしまいました。しかし魚容は、そだちがよかっので(ママ)、道々ものごいしてあるくのがはずかしくて、そんなことはとてもできません。そんなわけで、ひどくひもじくなり、富池鎭というところの、吳王廟というお宮まできたときには、とうとう、立ってもいられないくらいになりました。
ここで、このお話に関係のふかい、吳王廟のことを、ちょっと申しておきましょう。
吳王廟は、洞庭湖にそそぐ、楚江という川にそった、富池鎭という町にあります。三国時代(千六七百年前)の吳の国の将軍だった甘寧という人をまつったお宫で、宋(八百数十年前)のとき、神風をふかせて、船の往復をたすけたというので、評判になりました。それからというもの、日本でいえば、金比羅さまのように、船のりの神さまとしてあがめられ、たいそうあらたかだということでした。そこで船が廟のまえの川すじをすぎるときには、かならずお参りして、水路の平安をいのるのが例となっています。
廟のかたわらの林には、数百羽ものカラスがすんでいて、往来の船がありますと、二、三里(中国の一里は、三分の二キロメートル)も遠くから出むかえて、帆柱のうえで、むらがってさわぎます。すると船中の人々は、おもいおもいに肉を空中に投げあげます。カラスのむれはこれをうけて、百にひとつも落さないということです。船びとたちは、このカラスたちを、吳王の神の使だといつています。――
さて魚容は、ともかくも、神前にぬかづきましたが、落第したくやしさや、おなかのへった苦しさに、何をいのったやらもわからず、そのまま、たおれるように横になってしまいました。そしてふと気がつきますと、ひとりの男が、じぶんを引ったてるようにして、神殿のなかへはいっていきました。ふと見ると吳王の神の像は、生ける人のようであります。その男はひざまづいて、
「黒衣隊のうちのものが、またひとり欠けましたから、この男を補充にいたしたいと思います。」
と申しあげると、吳王はうなずいて、おゆるしになりました。するとさっそく、黒い衣がさずけられます。魚容が身につけてみますと、たちまち変わってカラスとなりました。羽ばたきしてとびたつと、カラスの仲間が、むらがっていたので、いっしょになってとんでいきました。カラスたちは、帆柱に分かれてむらがり、船の上の旅客たちが、てんでに肉を投げてくれるのを、空中にむらがりながらうけては食い、うけては食いしています。
そこで魚容も、はずかしくは思いましたが、やはりそのまねをしているうちに、おなかが一ぱいになりました。で、とんでいって、木のこずえにとまり、とても得意になっていました。
こうして、二、三日たちますと、吳王が、魚容につれがないのを、かわいそうに思って、一わの雌ガラスをめあわせてくれました。これが竹青という名で、おたがいに愛しあって、とてもたのしくくらしました。
魚容は、食物をあさりに出たとき、なれなれしくして、用心をしないことがよくあるので、竹青はしじゅう注意をしましたが、なかなかききませんでした。
ある日のこと兵士らが、船にのつてそこを通りました。そして、船の上の兵士が魚容を撃ったのが、胸にあたりました。が、さいわい竹青がかけつけて、魚容をくわえてとび去ったので、捕えられることだけはまぬがれました。カラスの大群はこれをみて怒り、どっと羽ばたきして波をあおったので、波がわきおこって、兵船はみな、くつがえってしまいました。
竹青はえさをとってきては、口うつしに魚容にたべさせていましたが、魚容のうけた傷は、とてもおもかったので、一日たつと死んでしまいました。
――と、このときふと、夢がさめたように気がつくと、なんと魚容のからだはあいかわらず廟のまえに、よこたわっているのでした。
それよりまえ、土地の人々は、魚容の死んでいるのを見いだしましたが、どこの者ともさっぱりわかりません。なでてみますと、まだ冷えきってはいなかったので、ときどき人に見せにやって いますと、それが今生きかえったのです。 で、いろいろとたずねて、事情がわかりましたので、魚容のためにお金をあつめて、かれを家へおくりかえしてやりました。
三年後のことです。魚容はまたこの地方を通ったので、吳王廟にお参りしました。そして、食べ物をおそなえし、カラスたちをよびあつめて、たべさせてやりました。そして、
「竹青が、もしこの中にいたら、どうぞ、あとに残っていておくれ。」
と、いつていのりましたが、食べてしまうと、カラスたちは、みなとんでいってしまいました。竹青はいなかったものと、思われます。
その後魚容は、すいせんされて、都で役人になり、その帰途また吳王廟にお参りしました。そして供物にヒツジをそなえ、そなえおわってから、たくさんの食べ物を用意して、カラスの友だちにごちそうして、また、おなじように、いのったのでした。
その夜は、洞庭湖の水辺の村に、船をつないでとまり、あかりをつけて船の中にすわっていますと、たちまち飛鳥のように、ひらりと机のまえへ落ちたものがありました。見ると、二十ばかりの、うつくしいひとです。にっこりして、
「お別れもうしてから、ご無事ですか。」
魚容がおどろいて、たずねますと、
「あなた、竹青をごぞんじありませんの。」
と、いいます。魚容はよろこんで、どこからきたかとたずねました。そのひとは言いました。
「わたくしは今、漢水の神女になっていますので、故郷にかえってくることは、めったにございませんの。でも、せんだって、カラスの使が、二度もあなたの、厚いおなさけを申しつたえましたので、お目にかかりにまいりましたのです。」
魚容は感動して、ますますよろこびました。ちょうど久しく別れていた夫婦のように、うれしさ恋しさに、たえなかったのです。そこで魚容は、いっしょに南へ帰ろうとしますと、女のほうは、 いっしょに西(漢江の方)へ、いこうとします。相談がまとまらないまま、その夜は船でとまって、さめてみますと、女はもう起きていました。魚容が目をみはって見まわしますと、そこはりりっぱな家のなかで、大きなしょく台に火がきらきらとかがやいて、どうしても船の中とはおもわれません。おどろいて起きあがって、
「ここは、いったいどこなんだい。」
と、たずねますと、女はわらっていいました。
「ここは漢陽(漢江の南岸の町)なのよ。わたくしのおうちは、あなたのおうち、でしょ。南へいか なくたって、よくはございません?」
やがて夜があけてくると、腰元や、ばあやたちが、ぞろぞろとあらわれてきて、酒もりの用意ができました。ひろい床の上に、ゆったりしたテーブルをすえて、ふたりは、さしむかえで酒をくみました。魚容が、じぶんの供のいどころをたずねまずと、船の上にいますと答えます。また、船頭が久しくは待ってくれないだろうと心配しますと、竹青はいいました。
「よろしいんですの。わたくしが、あなたにかわって、お礼をいたしておきますわ。」
そこで、いろんな話をしたり、酒をくみかはしたりして、あまりのたのしさに、魚容は帰るのをわすれていました。
一ぽう、魚容の船頭が、目をさましますと、急に漢陽にきていたので、非常におどろきました。供のものが、主人をたずねてみましたが、かいもく行くえがわかりません。船頭はほかへ行こうとしましたが、ともづなが、かたく結ばれていて、とけなかったので、とうとう供のものといっしょに、船で留守していることにしました。
ふた月あまりにもなりました。魚容はふと帰りたくおもって、竹青にいうには、
「ぼくがここにいると、親兄弟との仲もたえてしまう。それに、きみとぼくとは夫婦とはいいながら、きみは、一度も、ぼくの家へ行こうとしないのは、どういうわけだね。」
竹青はいうのでした。
「わたしが行けないのを、そんなにおっしゃらないでください。わたし、ふつうの人間ではありませんので、今しばらく、おかあさまに、おあいしたくありませんの。それより、わたしをここへおいといて、あなたの別莊にしたほうが、よくはありません?」
「でもここだと、道が遠くて、しょっちゅう来ることが、できないじゃないか。」
と、残念そうにいいますと、竹青は黒い衣をとりだして、
「あなたの、あの吳王廟のときの衣がまだあります。もし、わたしのことを思い出してくださったら、これを着ればすぐこられますし、いらしたら、わたしが、あなたのために、これをぬがしてさしあげましょう。」
こういって、大そうめずらしいごちそうをならべて、魚容のために、送別の宴をひらいてくれました。そのうちに魚容は、醉ってねてしまい、さめると、からだは船の中によこたわっていました。みれば、洞庭湖の岸の、もとの泊り場所で、船頭も供のものも、いっしょにいました。
みんなは大いにおどろき、魚容に、どこへ行っていたかと、たずねるのでした。魚容はわざと、まゆをしかめて、じぶんでも、おどろいて見せました。まくらもとに、ひとつの包があります。あらためて見ますと、竹青が贈ってくれた、あたらしい着物や、靴下や、はきものなどで、れいの黒い衣も、やはり、たたんで、そのなかに入れてありました。
また、ししゅうした袋が、腰のへんにつってあって、なかをあけてみますと、お金がーぱいつまっていました。そこで南をさして船を出し、岸につくと、船頭には、たくさんのお礼をやって、魚容は家へかえっていきました。
わが家へかえってから、五、六カ月たちました。しきりに漢水のことが、思い出されてしかたがありません。で魚容は、こっそり黒い衣をだして、着てみました。と、両わきにつばさがはえて、たちまち空を切ってとんでいき、四時間ばかりもたつと、はやくも漢水の上に達しました。(洞庭湖の南岸から、漢陽までは、一直線で、二百三十キロほどもあります)輪をかいて、とびながら見おろしますと、はなれ島の中に、いくむねかの高殿が見えます。魚容は、思いきってとびおりました。と、腰元がはやくも見つけて、呼ばわりました。
「だんなさまが、おいでになりました。」
まもなく竹青がでてきて、おおぜいにいいつけて、魚容のために、黒い衣の結び目をほどかせました。と、からだの羽毛がばらりと、すつかりぬけ落ちるのを感じました。
竹青は魚容の手をとって、家のなかへはいっていきました。
「あなた、いいところへいらしたわ。わたし、きょうにも、生まれそうなのよ。」
魚容は、じょうだんにたずねました。
「はじめから赤ん坊かね、それとも卵かね。」
竹青はいいました。
「わたし、いまでは神になっているんですもの、みも骨も、もうかわって、以前とはちがいますわ。」
二、三日たつと、竹青ははたしてお産をしました。ふつうの、大きな赤ちゃんでした。魚容はよろこんで、漢産と名をつけました。
三日目には、漢水の神女たちがたずねてきて、衣服や、めずらしい物などを贈って、いわってくれました。神女たちは、みんなきれいで、年も三十以上のものはありません。へやへはいって、寝台のそばへより、おや指で赤ん坊のはなをなでて、勝手にめでたい名まえをつけたりして笑いました。
神女たちがいってしまってから、あの人たちは、いったいだれだい、と、魚容がききますと、竹青はいいました。
「みんな、あたしのなかまよ。一ばんあとの、はすの花のような白い衣をきていた方は、本にも書かれている名高い仙女ですわ。」
二、三カ月たつと、竹青が船で、魚容の帰りをおくってくれ ました。船は、帆やかじをもつかわないのに、ひょうひょうとひとりでに走るのでした。岸につきますと、ちゃんと馬を道ばたにつないで、待っているものまでありました。こうして魚容は、家に帰りました。
それからというもの、魚容はたえず往来していました。数年たつと、漢産は、ますますかわいくなったので、魚容のかわいがりようといったら、大へんなものでした。また魚容の母は、一度初孫のかおを見たいものだと、しじゅう思わない日はありませんでした。
こうした事情を、魚容が竹青につげますと、竹青はすぐ、子供の旅じたくをととのえ、父といつしょに子供をかえしてやりました。ただし三ヵ月のあいだという約束でした。
帰っていくと、魚容の母は、はじめて孫というものを見たので、かわいくてたまらず、はやくも十ヵ月あまりにもなりましたが、返すにしのびないでいました。するとある日のこと、にわかに病気になって、子供は死んでしまいました。母は心をいためて、なげき死するほどでした。魚容はそこで、竹青にそのことをいうために漢江へいきました。門をはいると、子供の漢産が素足のままで寝台の上にねているではありませんか。魚容は非常によろこんで、竹青にそのわけをたずねますと、竹青がいうのに、
「あなたが、久しく約束にそむいていらっしゃるので、わたし子供が恋しくなり、それでよびよせたんですの。」
魚容はそこで、母が子供をかわいがっているものだからと話すと、竹青はいいました。
「わたしが、もう一度赤ちゃんをもうけるまで、お待ちくださいね。そしたら、漢産は返してさしあげるわ。」
それから一年あまりしますと、竹青は男と女の子をうんだので、男の子を漢生、女のほうを玉佩と名をつけました。魚容はそこで、漢産をつれて帰っていきました。が、年ごとに三、四度も往復するのは、とても不便だというので、とうとう漢陽の町に家をみつけて、引っこしてきました。
漢産は大きくなると、郡の学校にあがりました。のち、竹青は、人間界には美しい娘はいないといって、漢産をまねいて、よめをめとらせ、そのうえで返してよこしました。よめの名は扈娘といって、やはり神女のうまれでした。
そののち魚容の母が死んだときには、漢生も妹も、みなきて、母のお祭りをしました。葬式がすむと、漢産はよめとともに、家にとどまり、魚容は漢生と玉佩とをつれて、竹青のあとをおって行きましたが、それからはもう、漢陽の家へは帰ってこなかったということです。