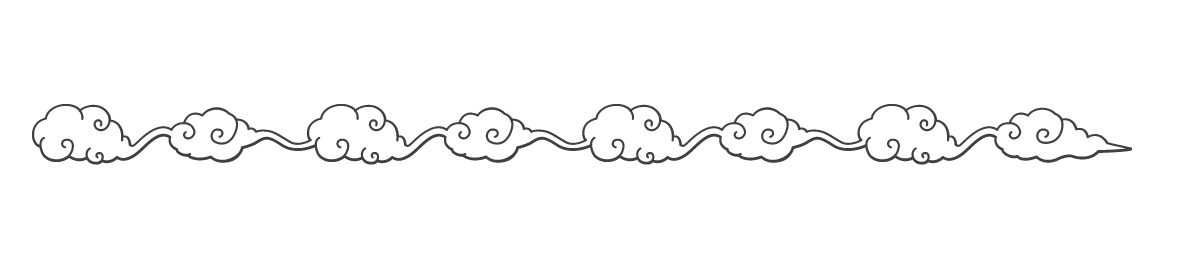伊藤貴麿関連資料の2回目は、前回と同じく『赤い鳥』に掲載された文章、第10巻6号(1923年6月)掲載の「水面亭の仙人」です。これも『聊斎志異』を原作として「自由訳」したもので、原作名は「寒月芙蕖」。この作品も『孔子さまと琴の音』(増進堂、1943年)を始め、いくつかの童話集に収められています。
今回も『赤い鳥』掲載時の文章をテキスト化したものです。原文からの変更点や、注意点につきましては、前回の投稿、伊藤貴麿関連資料(1)「虎の改心」をご覧ください。
水面亭の仙人 伊藤貴麿
一
昔支那に、老子といふ偉い仙人がありましたが、その方の敎が元になつて、後に道敎といふ敎が出來ました。道敎は、今でもさかんに支那人の間に信ぜられてをります。その道敎の修業をつんだ人で、昔から偉い仙人が澤山出ました。
今から数百年前に、支那の濟南といふ所に、或一人の穢い坊さんが、ひょつくりやつて來ました。町の人々は、その坊さんがどこから來たかも、又、名は何といふのかも知りませんでした。坊さんは夏冬なしに、袷をたつた一枚着たきりで、黄色い繩の帶を締めてゐました。別に下着も、ヅボンもはいてはゐません。髮はぼうぼうと生やしたまま、後に垂れて、よく馬鹿のやうに、その端を口に咬へたりしてゐました。いつも町をうろうろして、夜も、人の家の軒先などで寢てゐましたが、不思議なことに、冬雪が降つても、その坊さんの廻りだけはつもりませんでした。
初めてその坊さんが來た時、色んな不思議をあらはしましたので、町の人々は尊敬して、われ勝ちに喰べ物などを與へました。或時、町の無賴漢が、その坊さんに酒をやつて、不思議な術を敎へてくれと賴みましたが、坊さんは相手にしませんでした。無賴漢は腹を立てて、いつか坊さんをいぢめてやらうと思つて待つてゐますと、或日坊さんが川へ這入つて水を浴びてゐるのを見つけたので、
「さあどうだ、意地惡坊主、かうしてやらあ。」と言つて、川岸に脫いである坊さんの着物をさらつて行かうとしました。と、坊さんは、
「これこれ何をするのぢや、惡戯せんと、返しておくれ。その代り、お前さんに術を授けてあげよう。」と申しましたが、
「何ッ糞坊主、てめぇの言ふことなぞあてになるものか。」と言つて、着物を抱へて走り出しました。すると、不思議なことに、坊さんの繩の帶が見る見る大きな蛇に變つて、無賴漢の首にぐるぐる卷き着いたので、無賴漢は立ちながらぐつと息が詰つて、眞蒼になりました。蛇は猶もしうしう音を立て、鎌首をもたげて、焰のやうな舌をペラペラとはきますので、無賴漢はぶるぶる顫へ出し、地面の上にぺつたり坐つて、許しを乞ひました。すると坊さんは、笑ひながら着物を着て、その蛇を腰に卷いたかと思ひますと、どうでせう、それは元の繩の帶になつてゐました。
二
それから、この坊さんの名前は段々高くなつて、町のお役人や、紳士達は、爭って坊さんを招待して、色々敎を聽きました。そして、御馳走をして客でも呼ぶ時には、いつも坊さんをも招いて、あつくもてなしました。
すると或日、坊さんがやって來て、
「いつも、手前ばかり御馳走になって相濟みません。今度はいつか水面亭でお返しをいたしませう。」と言つて、立ち去りました。その後、或日のこと、町の紳士達は自分の机の上に、誰が置いて行ったとも知れない手紙が載つてゐるのを見て、びつくりして開けて見ますと、それは坊さんからの招待狀でした。
それで、その日町の人達が打ち揃つて、水面亭へ行つて見ますと、坊さんはやはり穢い着物を着たままひよろひよろと出て來て皆を迎へました。皆がお堂の中へ這入つて見ますと、部屋の中は空つぽで、椅子も何もありません。
「いやはや、これでは碌なもてなしは出來さうにもない。」と呆れ果ててゐますと、坊さんは客人達を振り返って、
「手前は貧乏ですから、召使がございません。どうか、お客人達のお供を拜借したいものです。」と言って、壁の上に一對の扉を描いて、指でこつこつと敲きますと、あら不思議や、その扉がぎーッと開きました。皆はびつくりして、驅け寄つて中を覗いて見ますと、どうでせう、紫檀の椅子や、眼もさめるやうな美しい覆ひのかかつたテイブルや、おいしさうな御馳走や、翦翠や琥珀を溶いたやうなお酒が、一ぱいに列んでをります。そこで、お供の者がそれ等をいちいち運び出して、やがて大きな宴會が開かれました。
元來水面亭といふのは、大きな湖に面してゐて、每年七月頃には、紅白の蓮の花が、見渡すかぎり一面に、咲き亂れるのですが、丁度その時は、まだ春の初めで、やつと水がぬるんで湖の面が靑み渡り、岸の柳が美しい靑い糸をなびかせてゐる位でした。
その時酒に醉つた一人の客が窓の方に寄つて、
「やあ、絶景々々、然し、花がまだ咲かないので淋しいなあ。」と申しました。皆も、こんな愉快な日に、湖水に花がないのは物足らないと思ひました。と、暫くして、一人のお供の者が驅け込んで來て、
「旦那、花が、花が……。」と申しますので、皆はびつくりして、窓を開けて眺めますと、湖面は千朶萬枝、白い玉を連ね、赤い焰が燃え立つたかのやうな花盛りで、南風がさはやかに頰を撫で、その良い香りは、心の底までしみ透るやうでした。
客人たちは有頂天になつて早速供の者に舟を出させて、蓮の花を取りにやりました。眺めてゐると、舟はだんだん進んで、花の間をあちこちと漕ぎ廻つて、やがて花の中に埋もれたやうに見えました。暫くして舟は歸つて來ましたが、舟に乘つてゐた者たちは、ぽかんとして空手で岸に上つて來ました。皆がわいわい言つて罵りますと、蓮を取りに行つた者は、
「私共が、花が北にあると思つて北へ行つて見ると、いつの間にか消えて、南の方へ移つてをります。それで南の方へ漕寄せて見ますと、又いつの間にか消えてしまひます。」と言つて、ぼんやりしてゐます。客人たちがあきれ返つてをりますと、坊さんは、
「花は皆あなたがたの心の幻かな。」と言つて、からからと笑ひました。そして、酒盛が終る頃には、北風がさつさつと吹き起つて、焰のやうな花も、一面に湖を覆つてゐたみづみづしい葉も、ふつと搔き消すやうに消えてしまひました。
三
かういふことがあつて以來、町の長官は非常に坊さんを尊つて、自分の屋敷に連れて歸つて、毎日一緖に語るのを樂にしてゐました。
或日、その長官の家に客があつて珍重してゐた良いお酒を出しました。然し、長官はいつもそのお酒を惜しんで、ちびちびしか出さないのです。お客がもつと飲みたがると、いつも、
「もうおしまひおしまひ。」と言つて手を振りました。その日も、お客が酒を飲み足らなさうにしてゐると、傍に居た坊さんが笑ひながら、
「私も一ばい御馳走をしませうかな。」と言つて、テイブルの上の德利を、自分の袖の中に入れて、又直ぐ取り出して、皆についで廻りますと、酒はいつまでもつきないで、後から後から、こんこんと湧いて出ました。客人たちはあつけに取られましたが、さて味つて見ると、前の酒と、香りといひ、味といひ、ちつとも變りません。皆は十分に醉ふまで飲んで歸つて行きました。
これをぢつと見てゐた長官は、これは坊さんが妖術を使つて、きつと自分の酒を盜んだに違ひないと、穴蔵へ行つて調べて見ますと、瓶の封はちやんと元のままであるのに、中の酒は一滴もなく、空つぽになつてゐました。これを見た長官はかつと怒つて、
「おのれ、恩知らずの、横着者め。」と言つて、杖をとつて打ちますと、返つて自分の腰に、びんと痛みを感じました。二度三度鞭打つてゐるうちに、坊さんがうんうんうなつて苦しがると同時に、自分の腰の肉も裂けて、だらだらと血が流れて來るので、どうにも爲樣がなく、鞭打つことをやめて、坊さんを表へ追つ拂つてしまひました。
坊さんは表へ出たかと思ふと、風のやうにどこへ行つたか解らなくなうました。そして再びもうこの町へは姿を現しませんでした。
それからずつと後に、この町の人が、南京といふ所へ行つたことがありましたが、或街角で、ひよつくり、その坊さんに逢つたといふ事です。その時、坊さんは元のやうに、ぼろの着物を着て、繩の帯をしめてゐたさうです。そして、何を訊ねても、ただ笑つてばかりゐて答へなかつたさうです。(をはり)