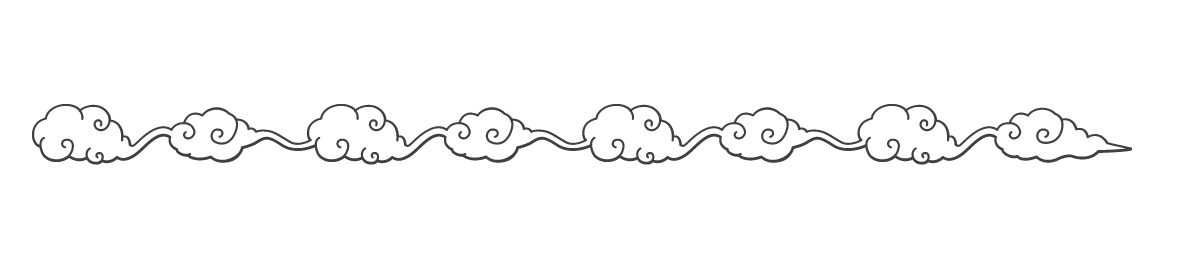伊藤貴麿関連資料6番目も『聊斎志異』の翻訳です。今期は「勞山道士」。しばらく『聊斎志異』の翻訳を載せていこうと考えています。
さて、この翻訳は『住宅』という雑誌に1922年8月に掲載されました。『住宅』は基本的には大人向けなのですが、家族全体で読まれることを想定していたのか、童話がよく掲載されていました。この「労山道士」も「童話」として掲載されており、私が今まで見た中では、伊藤貴麿の童話(児童向け読み物)の最も早いものです。
同じ月には以前に掲載した「聊齋妖話」(「胡四姐」「畫皮」の2編)が雑誌『新小説』に掲載されており、この時期『聊斎志異』がマイブームだったのかもしれません。
勞山道士 伊藤貴麿
私の村に王生と云ふ者があつた。彼は或る舊家の七男で、若い時から道を慕つて居た。或時、勞山に多くの仙人が居るといふ事を聞いて、笈を負ふて修道に出かけた。頂に登つて見ると、一つのお堂があつてなかなか幽邃である。一人の道士が薄團の上に坐つて居た。長い髮がうなじ迄垂れて、顏色さわやかである。王生はお辭儀をして、一緖に話して見ると、甚事理に徹して居るやうであつたから『どうかお師匠樣になつて下さい。』
と、王は賴んだ。すると道士は云つた。
『お前さんは懶け者らしいから、恐らく苦業が力まるまい。』
『いえ、大丈夫で御座います。』
と王は答へた。
其の門人は甚多くて、夕方に皆歸り集つて來た。王も一緖に其の中にまぢつて師弟の禮をとり遂にお堂の中に留まる事になつた。翌朝未明に道士は王を呼びつけて、斧を與へて、皆と一緖に薪を取にやつた。王は謹んで敎を受けて、一ケ月ばかりを過したが、手足が傷んで水泡が出來て、其の苦し味に溜りかね、心の中で歸り度いものだと思つた。
所が或る夕方、仕事から歸つて見ると、二人の見馴ない人が、師匠と一緖に酒を酌み交して居た。日は已に暮れて居るのに、末だ燈りがつけてない。すると師匠が紙を鏡のやうに切つて壁にはり着けた。とたちまち月光が輝き出して、玉蜀黍のひげでも見える位になつた。こうして門人達は周圍に集つて來て、もてなしに奔走した。すると一人の客人が、
『こんないい晚は、皆一緖に樂を極めなければいけない。』
と云つて、卓上の酒壷を取り上げて、門人達に與へて、十分飮ませる事にした。王は心に思つた。皆で七八人も居るのに、壷の酒がどうして皆に行きわたるだらう。それで皆盃を求めて、我れ勝ちにと、樽が 空になるのを恐れて、競ひ飮むこと入りかわり立ちかはりしたが、酒の量が少しもへらないので、不思議なことだと思つて居ると、突然又一人の客人が、
『月の光を賜はつて辱いが、お互でかうして飮んで居るのは寂しいものだ。どうして嫦娥を呼ばないんだい。』
と云つて箸を取つて、月中に擲打つと、たちまち一人の美人が光の中から現れて來た。初めは一尺にも足らなかつたが、地上に下り立つた時には、人と同じだけの大きさになつて居た。なよなよとした腰、秀でたうなじ、翩翩として霓裳の舞を舞ふのである。やがて歌ひ出した。
仙仙乎
而還乎
而幽我於廣寒乎
汝、仙よ!仙よ!
速に我れ歸り來なん
寂し冷し我が月の館(大意)
其の聲の淸越にして烈しいこと正に簫管を吹くが如くである。歌ひをさめて、くるくるつと迴つて立上り、身を躍らして卓上に飛上つた。喫驚して見て居る間に、又元の箸となつた。そして三人はからからと笑ひ出した。
又一人の客が云つた。
『ああ今宵は愉快だつた。が未だちと飮み足りないね。お別れに月宮殿で飮まうじやないか。』
かう云つて、三人は席を移して、漸く月中に入つて行つた。門人達には、三人が月の中に坐つて飮んで 居るのが見えて、鬚も眉もまるで鏡の中の影のやうにはつきりして居た。
やがて、月が段々暗くなつて來たので、門人が燈火を附けて來て見ると、士が獨り坐つて居るきりで、客の姿は搔き消したやうである。然し卓上には猶酒肴の跡が殘つて居て、壁の上には、お月様だつた鏡のやうに圓い紙があるばかりであつた。道士は皆に問ふた。
『飮み足りたかね。』
『はい、十分頂戴致しました。』
『そんなら早く寢て、明日の薪取りに後れないようにね。』
皆はかしこまつて退いた、此の事があつてから、王は竊に忻慕の念が生じて、もう歸りたいとは思はなくなつた。
それから、又一ケ月程經つた。又王はとても苦業を忍ぶ事が出來なくなつた。然も道士は一つの術をも授けては吳れない。もう待ち遠しくて溜らなくなつたので、師に云つた。
『私ははるばる數百里、仙師に業を受けに參つたものです。縱ひ長生の術を得ない迄も、幾分傳習致す所が御座いましたら、せめてもの慰めとなります。今迄二三ケ月を經ましたが、每朝早く樵りに出て、暮れに歸つて來るに過ぎません。私は家に在つた時は、こんな苦みを致した事は御座いません。
すると道士は笑つて云つた。
『俺しは初めにお前に云つたじゃないか、とても辛抱が出來まいと、やつぱり其の逋りだ。明朝は早々お前を歸してやらう。』
『私はお側で長らくお仕へ致しました。鳥渡した技でも授けて下さらば、來た甲斐があると云ふものです』
『どういふ術か欲しいのかね。』
『いつも私が見て居りますのに、お師匠樣かいらつしやる所、牆も壁も遮る事が出來ない有樣です。どうぞそれをお授け下すつたら幸です。』
道士はやはり笑つて承知して、王に秘訣を授けて、自分で咒ひを唱へさせて、叫んで云つた。
『入れ!』
王は牆に面したが、どうも入る事が出來ない。師は又叫んだ。
『試しには入つて見ろ!』
王は徐には入らうとすると、牆につかへて了つた。其の時師は叱咤した。
『首を垂れて突入するんだ!ためらつて居ちやいかん!』
王は牆を去る事數步、奔つて入ればまるで、空虛無物の境を行くやうで、邊りを見迴すと、果して身は牆の外に在つた。彼は大いに喜んで、入つて師に謝した。
『歸つてからも、行ひを愼まなければ駄目になるぞ!』
と師は云つてそれから王に幾らかの族費を與へて歸らした。王は家に歸つてから、俺は仙人に遇つて、 堅い壁をぬける術を授かつて來たんだぞと云つて自慢した。彼は妻が信じないものだから傚つて來た方法通りにして、牆から數尺離れて、奔つて突入した。と、頭を堅い壁にぐわんとぶつつけて、ぶつ倒れた。妻が扶け起して視ると、額の上が腫れ上つて、巨い卵をくつ附けたやうだつた。妻が揶揄ふので、王は慚ぢ忿り、道士の碌でなしを罵つたが、何とも仕樣もなかつた。