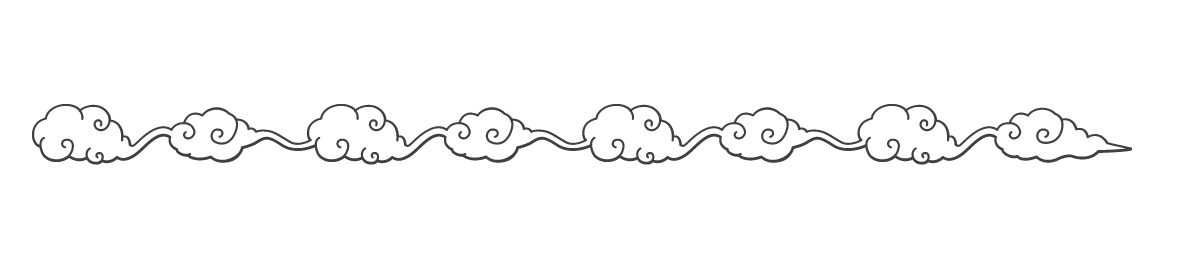伊藤貴麿関連資料の3回目。今回は雑誌『新小説』第27巻8号に掲載された「聊齋妖話」から「胡四姐」です。
「聊齋妖話」は、その表題のとおり、『聊齋志異』を訳したもので、この話と「畫皮」が訳されています。今回はそのうち、「胡四姐」の部分のみを掲載しました(「畫皮」は次回)。
なお、踊り字(繰り返し記号)は通常表記にし、Unicodeに無い異体字は正字を使用しましたが、それ以外は原文どおりです。
聊齋妖話 伊藤貴麿
胡四姐
泰山の尙生と云ふ靑年が、獨り靜かに書齋に籠つて居た。恰度頃は秋の夜で、銀河は高く澄み、明月は耿々として天に懸つて居たので、彼は花蔭を俳徊して、切りに空想を恣にして居た。と忽然として一人の女が垣を踰えて來て、
「秀才《あなた》は何をそんなに考へて被居るの。」
と云つて、につこりした。彼がよく視ると、其の姿の美しいこと、まるで仙女のやうだつたので、非常に喜び、書齋に連れ込んで懇ろになつて了つた。
「私の姓は胡つて云ふのよ。そして三人目だから三姐つて呼ばれて居るのよ。」
と女は自分で語つた。彼が家を訊ねると、ただ笑つて居て云はない。彼も亦重ねて問ふやうな事はしないで、ただこれから、長く仲よくしようとだけ云つた。それから娘は毎晩缺さずやつて來るやうになつた。或夕べ二人はやはり戯れて居たが、彼は娘が可愛くて溜らなくなり、ぢつと眸を凝らして見詰めて居た。すると娘は嫣然《につこり》して云つた。
「どうしてそんなに妾を御覽になるの。」
「さあ、お前を見て居ると、紅い花と云はうか、碧い桃と云はうか、夜つぴて見て居ても飽かないね。」
「妾のやうなおかめでも、そんなに愛して下さるんだつたら、もし宅の四人目の妹を御覽になつたら、貴郞きつとびつくらなさるわよ。
と云ふので、彼はひどく好奇心をそそられ、これ迄未だ一度も拜顏の榮を得なかつた事を殘念に思つて、言葉を盡して賴んだ。すると翌晩、果して四姐も一緖にやつて來た。彼の女は未だほんの處女になつたばかりで、蓮花露を含み杏花霞にうるんだとでも云はうか、嫣然として笑を含んだ其の媚めかしさ較べる物もない程であつたので、彼は狂喜して座に招じた。三姐はいつものやうに彼と談笑したが、四姐はただ刺繡した帶を手に弄んで、俯向いて居るばかりであつた。やがて三姐は起つて別れを吿げるので、妹も一緖に附いて行かうとしたが、彼は彼の女を引留めて放さず、三姐の方を顧て云つた。
「お前何とか云つて吳れてもいいじやないか。」
すると三姐は笑ひ出して云つた。
「狂郎《このかた》がきつい御思召しだよ。妹子《おまえ》一人で少らく居たらいいじやないか。」
四姐は默つて何とも云はない。姉の方は遂に行つて了つた。
それから二人は、懇ろに歡好《なさけ》を盡したあげく、臂を引いて枕に替ゑ、身の上を打明けて、何の隔てもなかつた。
「私は狐ですのよ。」
と四姐は自分で云つた。然し、彼は其の美しさに惚れ惚れして、深く怪しみもしなかつた。それで四姐は云つた。
「姉さんは、そりや怖ろしいのよ。もう三人もとり殺したの。迷つた者はきつと死んでよ。妾まあこんなに溺愛《なさけ》を受けて、貴郞を見殺しにする事は出來ないわ。早く姉さんと切れて頂戴な。」
彼は喫驚して、どうしたものかと震ゑ上つた。
「妾は狐でも、仙人の正法を得て居ますから、お符を書いてあげませう。寢床の外に貼つてお置きなさい。きつと御利益がありますから。」
と云つて、四姐はお符を書いて吳れた。
曉になつて三姐が這入つて來た。そして、お符を見て後ずさりして、
「まあ婢子《あまつよ》の恩知らずが新郞《をとこ》に惚れて、私を割くんだよ。私が兩人《ふたり》にしてやつた事を考へて見るがいい、よくもこんな眞似が出來たものだね。」
と罵つて逃げて行つた。
それから二三日經つて、四姐は他所へ行く事があつて、一日置いての夜を約束した。其の日彼はふと門を出て、其所らを眺めて居た。山の麓に古い樫の木がある。其の茂みからひよつくり一人の少女が出て來たが、亦なかなか捨て難い器量である。彼の女は彼に近附いて来て、
「秀才《あなた》、何も胡家の姉妹ばかりを思つて居るにあたらないじやありませんか。彼の人達は貴郞に一錢だつて贈つた事はないでせう。」
かう云つて、彼に錢一貫文を與へて又云つた。
「先歸つて、良い酒を買つといて下さい。私は私でちつとばかり御馳走を持つて行きますわ。ね一緖になにしませう。」
彼は錢を懷にして歸つて、云はれた通りにした。やがて約束通り女はやつて來て、卓の上に、灸つた雞と、鹽豚の肩の肉を列べて、庖丁をとつてこまかに刻んで料理し、それから酒をくみ、戯れて、よくよく歡洽《たのしみ》を極め、やがて燈りを消して………………散々巫山戯て、漸く夜明けになつて起きて、寢床の端に掛けて、靴を履いて居ると、突然人聲がして來たので耳を傾けた。幃幕《とばり》の中へ這入つて來たのを見ると、胡姉妹であつた。これを見ると女は慌て出して、靴を牀の上に遺したまま遁げ出した。姉妹は遂ひ乍ら罵つて云つた。
「下種《げす》狐め!よくもよくも人と一つ所に寢たね!」
かう云つて追つて行つたが、暫くして引返して來て、彼を怨んで云つた。
「貴郞は、直ぐもう下種狐などと匹偶《いつしよ》になつたりして、私もうもういや!」
彼の女は悻々《ぷんぷん》して行つて了はうとした。彼は惶て驚き、身を投げて、なだめつすかしつして哀願した。三姐も傍から口添へして吳れたので、四姐の怒りは稍解けた。そして初めと同じやうにいい仲になつた。
或日陝人が驢馬に騎つて門前に來て云つた。
「私は妖怪を尋ねて、朝に夕べに旅して居る者ですが、今初めて搜し的てました。」
尙生の父は、妙な事を云ふものだと、何所から來たかと訊ねると、
「私は或時は山を行き或時は海を行き、四方に遊歷して、一年の中、八九ヶ月は鄕里から離れて居ました。妖怪に弟をとり殺されまして、恨みに絕えず、必ず尋ね出して皆殺しにせんものと、はるばると旅しましたが、今迄皆無解りませんでした。所が今貴方の宅にそれが居るのです。殺して了はなければ、私の弟の二の舞のやうな目に會ひますよ。」
恰度其の時、尙生は女と密會して居た。父母はそつとこれを見て、客の言葉を聞いて大いに懼れ、客を延き入れて、魔除けをさせる事にした。客は二つの瓶を出し地上に列べて、やや長く呪文を唱へて居たが、やがて黑い霧の四つの塊りが、分れて瓶の中へすうつと這入つて行つた。
「うまい、皆つかまへた!」
客は喜んでかう云つて、そして、猪の脬《あぶら》で瓶の口を塞ぎ,固く封緘して了つた。尙生の父も亦喜んで、客を引留めて御馳走を出した。
尙生は溜らなくなつて、瓶に近附いて、そつと耳を付けて見た。すると四姐が瓶の中で云つてるのが聞えた。
「貴郞は恩知らずね! 坐つて默つて見て居ると云ふ法があるものですか!」
彼はもう溜りかねて、急いで封を開いたが、結び目がどうしても解けない。再び四姐が云つた。
「そんな事をしたつて駄目、祭壇の上の旗を倒して、針で脬に孔を開けて下すつたら出られるのよ。」
彼が其のやうにすると、果して白い煙が一と筋、孔中から出て、空へ消えて行つた。
客は出て見て、旗が倒れて居るのを見て、喫驚して云つた。
「やあ。遁げた! これは貴方の息さんの爲業に違ひない。」
そして瓶を搖つて、屈んできき耳を立てて云つた。
「幸ひに、一匹だけ逃しただけだつた。其奴は不死の力を得て居る奴だから、まあ赦してやつてもよいわい。」
かう云つて、瓶を携へて往つて了つた。
其の後、尙生が畑で傭人の麥を刈るのを監督して居ると、遙かに四姐が樹の下に坐つて居るのを見たので、彼は近附いて行つた。彼の女は彼の手を執つて、慰め問ふて云つた。
「お別れしてから、もう十年になりますのね。私は今ではもう仙人の修業が積みましたが、貴郞が未だすつかり忘れて被居らないと思つて、鳥渡御目にかかりに来ましたのよ。」
彼は一緒に歸らうとしたが、女は云つた。
「妾は昔の妾では御座いませんの、此の世の塵に染まる事は出來ませんわ。後程又御逢ひしますわ。」
かう云つたかと思ふと、其の行くへが解らなくなつて了つた。
後亦二十餘年,彼が適ま獨居して居ると、四姐が外から這入つて來るのが見えた。彼は喜んで一緒に語らつた。女は云つた。
「私は今では仙人となりましたので、もう二度と此の世に降りて來る事は出來なくなりました。ただ貴郞の情に感じましたので、貴郞の死期をお知らせしに來たのですわ。早く後の事を處分なさい。嘆くものじあありません。貴郞も鬼藉にお這入りになれば、妾どうでもしてあげられるのよ。」
そして彼の女は別れて往つた。彼の女の云つた冬至の日に、彼は果して死んで往つたと云ふ事である。
(「畫皮」につづく)